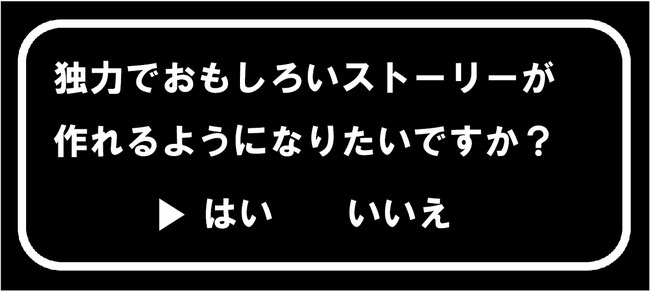1、話の前後で誰かの心が変化する
さて、これから話の作り方を解説していく訳ですが、
そもそも、話って何だと思います?
意外と、そんなこと考えたことはないのではないでしょうか?
結論から言いますと
とても大雑把に言ってしまえば、
「前後で心がかわる話」が話です。
実例を見てください。(余計な印象がつかないように記号的に描いています。)

なんだこれは・・・!バカにしてんのか!
と思うとおもいます。
でも、これが実は話の最小単位なんです。
例外は常にありますが、話の中では登場人物の心情が必ず変わるのです。
変わらないものはストーリー漫画でないか、天才的な何かか、的外れの作品かです。
これが、法則1「話の前後で誰かの心が変わる」です。
ここで「主人公の心が変わる」としないで「誰かの」としたのは訳があります。
主人公の心が変わらなくてもいいのです。
サブ主人公の心が変わる、敵の心が変わる、など主人公以外の心が変化する場合もあります。
これも実例を見たほうが早いです。

登場人物を追加しました。
黒の心は変化しません。
白の心が変化します。
黒が主人公だと、
これはヒーローものになります。
白が女の子だと女の子を助ける話になります。
白が男の子だと、友達や仲間などを助ける話になります。
白が主人公でも成り立ちます。
その場合黒はアドバイザーです。
たとえば、スポーツ漫画で、成績が出せず苦しんでいる主人公が
監督の助言でうまくなる、女の子の応援でがんばるなどです。
黒が主人公の場合は、強い主人公が周りを勇気付けて敵を倒すジャンプっぽい感じになります。
白が主人公だと、よわっちい主人公ががんばって強くなるサンデーっぽい感じになります。
余談ですが
マガジンっぽい話はジャンプ型で、主人公をDQN的な感じにするとなる気がします。
チャンピオンはサンデー型で、主人公を変態にするとそうなる気がします。
余談でした。
ミステリーとか探偵ものだと、主人公の心は変化せず、
犯人や被害者の心が変わったりします。
心の変化の仕方もさまざまで、
「嫌い→好き」なら恋愛もの、
「殺してやる→許す」ならサスペンス、
「無理に決まっている→やってみる!」なら何でも応用が利きます。
便利なのは「おまえは認めない→認める」とか。
作品の対象年齢が高くなればなるほど、心の変化の内容は複雑になり、
低くなるほど単純になります。
(のび太「調子こく→反省」とか。)
現代が舞台でない話、たとえばファンタジーを描いている人は、
関係ない!と思うかもしれません。
でもどんな世界観でも、登場人物が人の心を持っていれば、
あまり予想外の心理変化は起きません。
ファンタジーならなおさら、普通の人の心の変化が虚構の世界にリアリティを与えます。
どんなジャンルでも、実はこの部分が一番大事です。
物語の最小単位が理解できましたか?
では次は法則2です。